
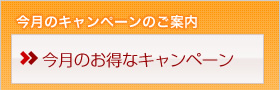
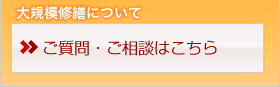


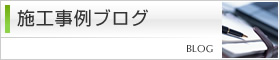
大規模修繕は、お住まいの方々の非常に大きな労力が必要とされます。保全工学研究所では、マンション管理組合の方、ビルオーナーの方が最適な大規模修繕を行うことができるようなご提案をさせていただきます。
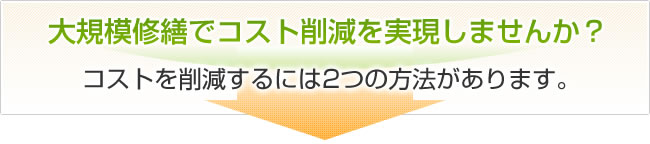
大規模修繕は周期的に行い、経年で低下した建物の性能を元に戻す重要な工事です。
大規模修繕には、建物・設備・駐車場・外構その他に分類され、その修繕周期も異なります。
作業足場を必要とする建物に関する修繕費用の割合が圧倒的に大きく、このコスト削減が長期修繕計画、修繕積立金等に大きく影響するといえます。
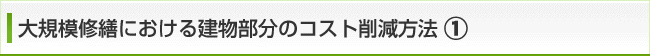
 建物部の修繕は、劣化部分の補修、シーリング打ち替え、屋上・バルコニー防水、外壁等の洗浄・塗装、鉄部・金物の塗装・補修などが行われます。それぞれ専門業者が実施するため、一般的には管理会社や建設会社が元請けとして施工管理を行っています。1社に任せきりにならず、他の工事業者との『合い見積もり』や工事と監理を分離する設計監理方式を含めて適正価格を目指すことが大切です。
建物部の修繕は、劣化部分の補修、シーリング打ち替え、屋上・バルコニー防水、外壁等の洗浄・塗装、鉄部・金物の塗装・補修などが行われます。それぞれ専門業者が実施するため、一般的には管理会社や建設会社が元請けとして施工管理を行っています。1社に任せきりにならず、他の工事業者との『合い見積もり』や工事と監理を分離する設計監理方式を含めて適正価格を目指すことが大切です。
次に、修繕工事の見積もりは、工事単価(工事の仕様により決まる)×数量で計算されます。この数量は部分的な建物診断結果からの推定値あるいは一般値(経験値)で計算されます。したがって、実施後には数量増減が伴います。近年の建物はその施工精度が向上しているため、見積もり時の数量よりも少なくなることが期待できます。工事の妥当性・実施後の数量チェックなど行うことで工事費の減額精算につなげることが大切です。
管理会社や施工業者に任せきりにせず、管理組合主体で活動することが重要ですが、最近では建物診断、工事監理、長期修繕計画の見直しまで対応する専門会社や建築設計事務所も増えています。
| 建物の日々の維持管理についてしっかりメンテナンスを行いましょう。 管理組合〜設計監理〜工事業者の相互信頼がコスト削減につながります。 |
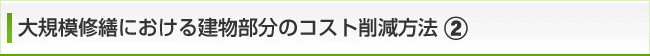
大規模修繕の周期は、9〜15年程度といわれています。
例えば、築後30年間でみると、10年周期では3回、15年周期では2回と1回違います。
建物部の大規模修繕費用は、1戸当たり平均100万円といわれており、30年で100万円の差が発生します。
修繕の周期は、必ずしも定期的に行うのではなく、定期報告などの法定点検の結果や事前の建物診断をもとに、各部位の劣化の程度を把握し工事の実施を決定します。診断結果の適正な判断から、大規模修繕工事の周期を少しでも長くすることができるといえます。建築基準法による建物の定期報告制度では、3年に1回の報告義務があります。H20.4の法改正で、「竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査する」ことが必要になりました。
壁面の全面打診等とは、一般に足場を架ける必要があると思われがちですが、赤外線サーモグラフィによる調査で代替することができると明記されています。
赤外線サーモグラフィによる調査では、建物全体の外壁のタイルの浮き・はく離が調査できるので、定期報告と兼ねて外壁の劣化の程度を把握することができます。
| 大規模修繕が必要かどうかを客観的に見極めるために、建物全体を赤外線サーモグラフィで撮影し、適切に判断しましょう。 |